東京・上野公園周辺で、開催中の注目の展覧会・展示ニュースをまとめました。美術館や博物館巡りの参考にご覧ください。
※展覧会やイベントの内容が変更されている場合がございます。最新の情報は各施設の公式ホームページなどでご確認ください。
2026年2月のまとめ
特別企画 日韓国交正常化60周年記念 韓国美術の玉手箱 ― 国立中央博物館の所蔵品をむかえて―
会期:2026年2月10日(火)~2026年4月5日(日)
会場:東京国立博物館 本館 特別1室・特別2室
東京国立博物館と韓国国立中央博物館は、昭和40年(1965)の日韓国交正常化から60年を迎えたことを記念し、韓国美術の展覧会を共同で開催いたします。
日本と韓国の歴史・文化は、互いに深く関わりあいながら発展してきました。両館は、それぞれを代表する国立博物館として、相互理解を一層深めるため平成14年(2002)に学術交流協定を結び、以来20年以上にわたって、研究員の相互派遣や共同調査、作品の相互貸借など多様な交流を積み重ねてきました。本展は、その成果の一つとして、両館が誇る所蔵の名品によって韓国美術の精華を紹介するものです。
第1章「高麗― 美と信仰」では、洗練を極めた高麗時代の仏教美術や金銀器・青磁を、そして、第2章「朝鮮王朝の宮廷文化」では華麗な宮廷絵画や服飾品などをご堪能いただきます。本展を通じて、日本のみなさまに韓国の歴史・文化の豊かさとその魅力を存分に味わっていただければ幸いです。
展覧会詳細:https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2735
KAKIEMON ―伊万里焼柿右衛門の世界―
会期:2025年11月11日(火)~2026年2月8日(日)
会場:東京国立博物館 本館 14室
17世紀初めに日本で最初の磁器がつくられた肥前有田地域では、17世紀半ばになると輸出向け磁器の生産が本格化します。輸出磁器は、当初、内乱により輸出が減少していた中国景徳鎮産の磁器を補うように生産されましたが、やがて中国の模倣にとどまらない独自の様式を確立していきました。その代表が、「濁手(にごしで)」と呼ばれる乳白色の地に、赤を主とする明るい色絵具を用いて余白のある構図で描く、いわゆる柿右衛門様式と称される色絵磁器です。これらはヨーロッパに数多く渡り、オランダ、イギリス、フランス、ドイツといった王侯貴族たちに受容され、実用だけでなく屋敷を飾る装飾品としても用いられました。またこうした輸出製品は、酒井田柿右衛門家の窯だけでなく周辺の地域一体の窯でもつくられ、その様相は生産地や消費地における出土品などからも明らかにされており、そのなかには色絵だけでなく上質の染付も含まれます。
本特集では、輸出磁器初期の作例から、よく知られる柿右衛門様式、加えて有田周縁でつくられた上質磁器、金襴手様式への移行期の作例、そして18世紀の中国での写しといった、関連作品も含めて「KAKIEMON」として紹介します。
展覧会詳細:https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2727
インドネシア・スマトラ島 織りと染めの世界
会期:2025年11月5日(水) ~ 2026年2月1日(日)
会場:東京国立博物館 東洋館 13室
インド洋と太平洋に浮かぶ島々で構成される、インドネシア。その西部に位置するのがスマトラ島です。日本よりも広い面積を有するスマトラ島には、さまざまな民族グループが暮らしており、地域によって多様な織りと染めの技法が認められます。たとえば、ろうけつ染め(バティック)や印金を駆使して製作された腰巻、あらかじめ染め分けた緯糸を使って文様を織り出した緯絣(イカット)、金銀糸を刺繡した女性用のスカートなど、島の南北で衣装の形や、用いられる染織技法が異なっている点が大きな特色です。
また、大航海時代以前より香辛料交易を介し、インド製の更紗がインドネシアの島々にも伝来しました。文様の類似性などから、インド更紗はインド ネシアのバティックと影響しあっていたことが推測されています。本特集では、スマトラ島の染織品の魅力を、20世紀初頭に撮影された着 装時の写真とあわせて紹介します。加えて、スマトラ製のバティックとスマトラ島伝世インド更紗をあわせて展示し、その関連性についても探ります。
展覧会詳細:https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2726
明末清初の書画―乱世にみる夢―
会期:2026年1月1日(木・祝)~2026年3月22日(日)
会場:東京国立博物館 東洋館 8室
本展示は、台東区立書道博物館との連携企画第23弾として開催します。
中国の明末清初(みんまつしんしょ)(17世紀前後)は、漢(かん)民族が統治する明(1368~1644)から満洲(まんしゅう)族による清(1616~1912)へと王朝が交替した激動の時代です。
書画をよくした漢民族の文人たちは、王朝の滅亡に際して、自らの立場の選択を迫られました。明と運命をともにして殉じた烈士(れっし)、清に抵抗する姿勢を貫き、当地で明への忠節を尽くした遺民(いみん)、海を渡った日本への亡命者、そして汚名を顧みず、清に降伏して明清両朝に仕えた弐臣(じしん)。彼らは不安定極まりない社会情勢のもと、それぞれの立場で葛藤を抱えて生涯を全うし、ときに胸中の複雑な想いを筆墨に託して、強烈な個性を発揮した書画に昇華させました。
この時期の書画には、金による装飾を施した料紙の金箋(きんせん)、滑らかで光沢のある絹織物の絖(ぬめ)など、煌(きら)びやかな材質の紙・絹が好んで用いられました。また、縦長の大きな長条幅(ちょうじょうふく)、扇形の扇面(せんめん)などの画面形式も流行します。「奇」すなわち独創性を重んじる風潮などを背景として、古典の様式をふまえながらも、連続する文字を一筆で書き連ねた連綿草(れんめんそう)や、デフォルメされた奇怪な造形といった、素材・形式を効果的に活かした新奇な作風を築いたものが少なくありません。
本特集では、明末清初の個性豊かな書画を、素材・形式と作風、そして作者の立場にも注目しながらご紹介します。乱世に生きた文人たちが、あたかも「夢―願望・空想・迷い・儚(はかな)さ」をみるかのように、書画に表そうとした多様なイメージをご覧ください。
展覧会詳細:https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2730
東京国立博物館
住所:〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9
公式サイト:https://www.tnm.jp/
アクセス(GoogleMap):https://goo.gl/maps/YWjaJoqwxGUJLaEM7
東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき
会期:2026年1月27日(火)~4月12日(日)
会期:東京都美術館 企画展示室
ヨーロッパ北部、スカンディナヴィア半島に位置する国スウェーデン。本展は近年世界的に注目を集める、スウェーデン美術黄金期の絵画を本格的に紹介する展覧会です。スウェーデンでは、若い世代の芸術家たちが1880年頃からフランスで学び始め、人間や自然をありのままに表現するレアリスムに傾倒しました。彼らはやがて故郷へ帰ると、自国のアイデンティティを示すべくスウェーデンらしい芸術の創造をめざし、自然や身近な人々、あるいは日常にひそむ輝きを、親密で情緒あふれる表現で描き出しました。本展はスウェーデン国立美術館の全面協力のもと、19世紀末から20世紀にかけてのスウェーデンで生み出された魅力的な絵画をとおして、自然と共に豊かに生きる北欧ならではの感性に迫ります。
展覧会詳細:https://www.swedishpainting2026.jp/
東京都美術館
住所:〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36
公式サイト:https://www.tobikan.jp/index.html
アクセス(GoogleMap):https://goo.gl/maps/STJUT3f1V3a47re27
オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語
会期:2025年10月25日(土)-2026年2月15日(日)
会場:国立西洋美術館 企画展示室
印象派といえば、移ろう光や大気とともにとらえた戸外の風景がまず思い浮かぶのではないでしょうか。とはいえ、彼らの最初のグループ展が開かれたのは、近代化が急速に進む1870年代のパリ。この活気に満ちた大都市や、その近郊における現代生活の情景を好んで画題とした印象派の画家たちは、室内を舞台とする作品も多く手がけました。とりわけ生粋のパリ市民であったエドガー・ドガは、鋭い人間観察にもとづいた、心理劇の一場面のような室内画に本領を発揮し、一方でピエール=オーギュスト・ルノワールは、穏やかな光と親密な雰囲気をたたえた室内情景を多数描きました。ほかにもエドゥアール・マネやクロード・モネ、ギュスターヴ・カイユボットらが、私邸の室内の壁面装飾を目的として制作した作品も少なくありません。印象派と室内は、思いのほか深い関係を結んでいたのです。本展では、「印象派の殿堂」ともいわれるパリ・オルセー美術館所蔵の傑作約70点を中心に、国内外の重要作品も加えたおよそ100点により、室内をめぐる印象派の画家たちの関心のありかや表現上の挑戦をたどります。オルセー美術館の印象派コレクションがこの規模で来日するのはおよそ10年ぶり。さらに今回、若きドガの才気みなぎる代表作《家族の肖像(ベレッリ家)》が日本で初めて展示されます。マネ、モネ、ルノワール、ポール・セザンヌらの名品も一堂に会するこの機会に、室内というテーマを通して印象派のもうひとつの魅力をぜひご堪能ください。
展覧会詳細:https://www.orsay2025.jp/
フランドル聖人伝板絵―100年越しの“再会”
会期:2025年10月25日(土)〜2026年5月10日(日)
会場:国立西洋美術館 本館展示室
ブリュージュのフルーニング美術館と国立西洋美術館には、キリストの使徒、聖ヤコブの生涯の物語場面を描いた板絵がそれぞれ所蔵されます(以下、ブリュージュ作品・東京作品)。両作品は1909年当時、ロンドンのファー画廊にありました。その後、ブリュージュ作品は1911年までにパリのクラインベルガー画廊へ移り、1912年にフルーニング美術館に入っています。クラインベルガー画廊が1911年に作成した目録に東京作品の記録はなく、これ以前に2点は分かたれていたと考えられます。東京作品は20世紀初頭に松方幸次郎によって購入され、日本に送られました。そしてその後、国内の個人コレクションを経て、2017年に国立西洋美術館に取得されることとなります。
2017年の取得に際して、国立西洋美術館では作品調査を実施し、その結果、東京作品がブリュージュ作品と、かつて同一の祭壇装飾ないし連作に属したものであることが確認されました。この再発見を機に企画された本展では、20世紀初頭にベルギーと日本に分かたれた二作品の100年越しの「再会」をはかります。また、2017年以降、フルーニング美術館、国立西洋美術館を中心に進めてきた作品調査の成果を、展示、講演会、論文集によってご紹介します。
展覧会詳細:https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2025flemish.html
物語る黒線たち――デューラー「三大書物」の木版画
会期:2025年10月25日(土)〜2026年2月15日(日)
会場:国立西洋美術館 版画素描展示室(常設展示室内)
この小企画展では、デューラーがみずから出版者となって1511年に刊行したいわゆる「三大書物」――つまり『黙示録』(ラテン語版再版)、『大受難伝』、『聖母伝』という、当時としてきわめて劃期的だった活字印刷本の木版画群を、一挙にすべてお披露目します。1959年に開館した国立西洋美術館は、近代美術ばかりでなくオールド・マスターの作品も本格的に収集してゆくという方針を1968年の着任後に打ちだした第二代館長の山田智三郎のもと、1970年度にデューラーの木版画連作『大受難伝』を取得しました(ただし、一葉のみは1974年度に購入)。これらは、それ以降に国立西洋美術館がオールド・マスターの版画コレクションを築いてゆくうえでの重要な出発点になったといえます。そして半世紀のときを経て、2020年度に『黙示録』、2022年度には『聖母伝』の購入が叶ったことで、われわれの美術館はついに、デューラーの「三大書物」の木版画をあまねく所蔵するにいたりました。
ご覧いただく「三大書物」の各木版画は、裏面や欄外にラテン語の活字テクストが印刷された1511年の正式出版時の貴重なエディションの作品となります。デューラーがそれらの木版画を物語連作としてのみならず、書物として発表することを念頭に置いて制作していたという事実を示すべく、エディションにこだわりながら、多年にわたって慎重に購入を進めてきたためです。本展ではまた、デューラーが『黙示録』、『大受難伝』、『聖母伝』を生みだすにあたって造形的に刺戟を受けたと考えられる先行世代の美術家たちの作品を導入部でご紹介します。くわえて、そうしたデューラーの「三大書物」の木版画に触発されてつくられた後続世代の産物もあわせて展示することで、造形思考の連鎖やその多元的なネットワークを浮かびあがらせます。
展覧会詳細:https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2025durer.html
国立西洋美術館
住所:〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7
公式サイト:https://www.nmwa.go.jp/jp/index.html
アクセス(GoogleMap):https://goo.gl/maps/qAq7EVGnuRjxwtRe9
特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」
会場:国立科学博物館 (東京・上野公園)
会期:2025年11月1日(土)~2026年2月23日(月・祝)
生命が誕生してから40億年、地球上では幾度も生命の危機が訪れました。それは主に地球外からやってきた小惑星の衝突や火山などの地球内部の活動によりもたらされましたが、ときに生命活動そのものが引き金になったこともあります。しかし生命は、その都度、したたかにそれらの危機を乗り越え、絶滅したグループに代わるグループが新たに繁栄することを繰り返すことで、多様に進化を遂げてきました。言わば、大量絶滅は生命の繁栄を促した現象だと捉えることもできるのです。本展では、その中でも規模の大きかった5回の「大量絶滅」事変(通称「ビッグファイブ」)を、化石や岩石に残された様々な証拠から紐解き、「生き物たち」の生存をかけた進化の歴史を辿ります。「ビッグファイブ」をテーマとする特別展は、国立科学博物館では初めてとなります。各種の古生物や火山、古気候・古海洋などを専門とする国立科学博物館の研究者10名による監修で、様々な角度から5回の大量絶滅の謎に迫ります。
展覧会詳細:https://daizetsumetsu.jp/highlights.html
企画展 ワニ
会期:2025年11月26日(水)~2026年3月1日(日)
会場:国立科学博物館(東京・上野公園)日本館1階企画展示室、中央ホール
太古の昔から姿をほとんど変えず、水辺に暮らしてきたワニ。爬虫類の中でもひときわ強い存在感を放っています。本展では、世界のワニの多様な姿や生態を、剥製や骨格標本、映像などを通して紹介するとともに、古文書に残る記録から人とワニとの関わりの歴史をひもときます。長い間“水辺の隣人”として人類と共に生きてきたワニの姿から、私たちと野生動物とのこれからの関係を見つめます。
展覧会詳細:https://www.kahaku.go.jp/event/nid00001559.html
国立科学博物館
住所:〒110-8718 東京都台東区上野公園7-20
公式サイト:https://www.kahaku.go.jp/
アクセス(GoogleMap):https://goo.gl/maps/zBoHtasXcNCq7FSt8
企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展 2026」
会場:藝大アートプラザ
会期:2026年1月24日(土)〜3月22日(日)
今年も開催!藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展。藝大アートプラザ・アートアワードは藝大の全学生を対象に開催される年に一度のアートアワード。今年度で20回を迎えます。本展はその入賞作品をすべて展示・販売するという年に一度の貴重な機会。未来のスターアーティストの原石がごろごろ?あなただけの大切な作品に出会う大チャンス?藝大アートプラザでまだ見ぬアーティストのまだ見ぬ作品を探してみませんか?
展覧会詳細:https://artplaza.geidai.ac.jp/column/29190/
安河内裕也個展「After Vision -天涯」
会場:藝大アートプラザ
会期:2026年2月10日(火)~3月1日(日)
私は人間と自然を達観し、相互の調和や平和の為のビジョンを描いています。版画では浮かぶイメージを練り上げ、銅やプラスチックに刻み込み、刷り上げます。ドローイングでは無秩序なペンの動きを、直接、紙に描き込みます。種としての人間の視点から、作品を見て、考えて頂けると幸いです。
展覧会詳細:https://artplaza.geidai.ac.jp/column/29482/
藝大アートプラザ
住所:〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内
公式サイト:https://artplaza.geidai.ac.jp/
アクセス(GoogleMap):https://goo.gl/maps/w6T4HWuMghT2xfAX7
-2026年1月末更新-
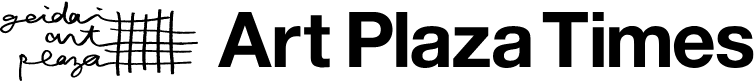

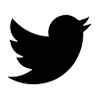 ツイートする
ツイートする
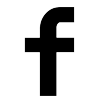 シェアする
シェアする
