東京・上野公園周辺で、開催中の注目の展覧会・展示ニュースをまとめました。美術館や博物館巡りの参考にご覧ください。
※展覧会やイベントの内容が変更されている場合がございます。最新の情報は各施設の公式ホームページなどでご確認ください。
2025年6月のまとめ
特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」
会期:2025年4月22日(火)~2025年6月15日(日)
会場:東京国立博物館 平成館 特別展示室
江戸時代の傑出した出版業者である蔦重こと蔦屋重三郎(1750~97)は、喜多川歌麿、東洲斎写楽といった現代では世界的芸術家とみなされる浮世絵師を世に出したことで知られています。本展ではその蔦重の活動をつぶさにみつめながら、天明、寛政(1781~1801)期を中心に江戸の多彩な文化をご覧いただきます。蔦重は江戸の遊郭や歌舞伎を背景にしながら、狂歌の隆盛に合わせて、狂歌師や戯作者とも親交を深めるなど、武家や富裕な町人、人気役者、人気戯作者、人気絵師のネットワークを縦横無尽に広げて、さまざまな分野を結びつけながら、さながらメディアミックスによって、 出版業界にさまざまな新機軸を打ち出します。蔦重はその商才を活かして、コンテンツ・ビジネスを際限なく革新し続けました。 そこに根差したものは徹底的なユーザー(消費者)の視点であり、人々が楽しむもの、面白いものを追い求めたバイタリティーにあるといえるでしょう。この展覧会では、蔦屋重三郎を主人公とした2025年の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(NHK)とも連携し、江戸の街の様相とともに、蔦重の出版活動をさまざまにご覧いただきながら、蔦重が江戸時代後期の出版文化の一翼を担っていただけでなく、彼が創出した価値観や芸術性がいかなるものであったかを体感いただきます。
展覧会詳細:https://tsutaju2025.jp/
浮世絵現代
会期:2025年4月22日(火)~2025年6月15日(日)
会場:東京国立博物館 表慶館
日本の木版画の技術は、江戸時代の文化の中で独自に発展し、浮世絵という力強く華やかな芸術を生み出しました。「浮世」という言葉には「当世風の」という意味があり、浮世絵 版画はまさにその時代と社会を色鮮やかに映し出すメディアでした。写楽や歌麿、北斎の浮世絵を生み出したこの高度な木版画の技術は、途切れることなく、現代まで職人たちに受け継がれています。山桜の版木を使い、和紙に墨と水性の絵具で摺り上げることで生まれるシャープな線や軽やかな色彩は、唯一無二のものです。伝統の技術は、同時代の人々の心をとらえる作品を生み出し続けることで、さらに次代へと継承されていきます。この展覧会は、伝統木版画の表現に魅了された様々なジャンルのアーティスト、デザイナー、クリエーターたちが、現代の絵師となり、アダチ版画研究所の彫師・摺師たちと協働して制作した「現代」の「浮世絵」をご覧いただくものです。総勢約80名のアーティストたちの木版画を通じて、現代から未来につづく伝統の可能性をご鑑賞ください。
展覧会詳細:https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2693
イマーシブシアター 新ジャポニズム~縄文から浮世絵 そしてアニメへ~
会期:2025年3月25日(火)~2025年8月3日(日)
会場:東京国立博物館 本館 特別5室
はるか1万年以上前から、日本の風土の中で、独自の美意識が受け継がれてきました。縄文土器、はにわ、絵巻、鎧兜、浮世絵、さらには世界で人気のアニメまで。NHKの高精細映像と技術を結集したイマーシブシアター「新ジャポニズム」。東京国立博物館所蔵の国宝や重要文化財を中心にした日本文化のタイムトラベルをお楽しみください。
展覧会詳細:https://immersive-tohaku.jp/
東京国立博物館
住所:〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9
公式サイト:https://www.tnm.jp/
アクセス(GoogleMap):https://goo.gl/maps/YWjaJoqwxGUJLaEM7
ミロ展 Joan Miró
会期:2025年3月1日(土)~7月6日(日)
会場:東京都美術館 企画展示室
1893年にスペインのカタルーニャ州に生まれたジュアン・ミロ(1893~1983)は、同じスペイン出身のピカソと並び20世紀を代表する巨匠に数えられます。太陽や星、月など自然の中にある形を象徴的な記号に変えて描いた、詩情あふれる独特な画風は日本でも高い人気を誇ります。そんなミロの創作活動は、没後40年を迎えたいま、世界的に再評価されています。本展は、〈星座〉シリーズをはじめ、初期から晩年までの各時代を彩る絵画や陶芸、彫刻により、90歳まで新しい表現へ挑戦し続けたミロの芸術を包括的に紹介します。世界中から集った選りすぐりの傑作の数々により、ミロの芸術の真髄を体感できる空前の大回顧展です。
展覧会詳細:https://miro2025.exhibit.jp/
都美セレクション グループ展 2025 Group Show of Contemporary Artists 2025
会期:2025年6月10日(火)~7月2日(水)
会場:東京都美術館 ギャラリーA・B・C
「都美セレクション グループ展」は、新しい発想によるアートの作り手の支援を目的として、当館の展示空間だからこそ可能となる表現に挑むグループを募り、その企画を実施するものです。「都美セレクション グループ展 2025」では、応募の中から厳正な審査を経て選ばれた3グループが展覧会を実施し、絵画、写真、映像、インスタレーション等によるさまざまな作品を展示します。
展覧会詳細:https://www.tobikan.jp/exhibition/2025_groupshow.html
東京都美術館
住所:〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36
公式サイト:https://www.tobikan.jp/index.html
アクセス(GoogleMap):https://goo.gl/maps/STJUT3f1V3a47re27
西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館 vs 国立西洋美術館
会期:2025年3月11日(火)〜6月8日(日)
会場:国立西洋美術館 企画展示室
本展は、米国のサンディエゴ美術館との共同企画により、同館と国立西洋美術館の所蔵する作品計88点を組み合わせ、それらの対話を通じてルネサンスから19世紀に至る幅広い西洋美術の魅力とその流れを紹介する展覧会です。サンディエゴ美術館は、主に1930年代を通じ、当時のアメリカ合衆国西部では随一の質と規模を誇るヨーロッパ古典絵画のコレクションを築きました。サンディエゴという土地の歴史・文化性や、篤志家たちの趣味を色濃く反映したユニークな内容を誇り、初期ルネサンス絵画やスペイン17世紀絵画などに多くの傑作を有しています。一方国立西洋美術館は、松方幸次郎の収集した印象派を中心とするコレクションに基づいて1959年に設立され、1960年代末から古典絵画の体系的な収集を開始しました。以降、歴代の館長や研究員の調査研究に基づいて、西洋美術史の主要な流派やジャンルを網羅にカバーする総合的なコレクションの形成を目指して収集活動を続けています。本展は、両館の所蔵する作品をペアや小グループからなる36の小テーマに分けて展示、比較に基づく作品の対話を通じ、ルネサンスから印象派に至る西洋美術史の魅力を分かりやすく紹介することを目指します。また両館は非ヨーロッパ圏においてヨーロッパ美術を収集した点においても共通します。その点に着目し、両館の持つ傑作を比較対照させながら、それぞれ西洋絵画がどのような目的や理想に基づいて収集されていったのかについても、紹介する予定です。なお本展開催中、サンディエゴ美術館所蔵作品よりさらに5点の絵画を西洋美術館常設展で展示し、さらなるコレクションの対話を試みます。これらを含むサンディエゴ美術館からの出品作49点は、すべて日本初公開となります。
展覧会詳細:https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2025dokomiru.html
梶コレクション展―色彩の宝石、エマーユの美
会期:2025年3月11日(火)〜6月15日(日)
会場:国立西洋美術館 版画素描展示室(常設展示室内)
2024年12月、当館に新たな工芸コレクションが寄贈されました。数にしておよそ150点。そのほぼすべてがエマーユの作品です。「エマーユ」は耳慣れない言葉かもしれません。これは仏語のカタカナ表記で、英語にするとエナメル、日本ではふつう七宝と呼ばれています。つまりエマーユとは、金属の下地にガラス質のうわぐすりを焼き付けた工芸品を意味します。寄贈者はジュエリーアーティストの梶光夫氏です。選りすぐられた珠玉のエマーユからなるこの新たな「梶コレクション」が、本展でデビューします。梶コレクションは19世紀後半から20世紀初頭のフランスで制作されたものが中心で、多彩なラインナップをそろえています。コインのような小さな単体や、ジュエリーに仕立てられたもの、小箱のふたを飾るもの、そしてカンヴァス画のような額縁に収められた大ぶりものまで、エマーユの姿形はさまざまです。その多くに、アール・ヌーヴォー時代の息吹を感じ取ることができることも、梶コレクションの大きな魅力のひとつです。今回の企画では、寄贈品以外に梶氏が所蔵するアルフォンス・ミュシャのポスターやエミール・ガレのガラス器、ルイ・マジョレルの家具等を加えて、当時の美術・工芸の豊かな世界の一端を感じ取ることができるような展示空間を演出します。エマーユの最大の魅力は鮮やかな色彩と繊細なきらめきです。そのまばゆい光を目にすると、美しさは物自体に宿るのではなく、輝きの中で生まれてくるような気がします。その意味では、エマーユも宝石も何ら変わるところはありません。そうした魅惑的な光に満たされた小さな展示室に、ぜひお越しください。
展覧会詳細:https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2025emaux.html
国立西洋美術館
住所:〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7
公式サイト:https://www.nmwa.go.jp/jp/index.html
アクセス(GoogleMap):https://goo.gl/maps/qAq7EVGnuRjxwtRe9
特別展「古代DNA ―日本人のきた道―」
会場:国立科学博物館 (東京・上野公園)
会期:2025年3月15日(土)~6月15日(日)
ホモ・サピエンスはおよそ4万年前に日本列島に到達しました。この「最初の日本人」の姿は謎に包まれていましたが、近年、沖縄県の石垣島で2万7000年前の人骨が発見されました。国立科学博物館では、古代ゲノム解析でノーベル賞を受賞したスバンテ・ペーボ博士のグループと共同で研究を進めており、この章では、その成果を紹介します。
展覧会詳細:https://ancientdna2025.jp/
気象業務150周年企画展「地球を測る」
会期:2025年3月25日(火)~6月15日(日)
会場:国立科学博物館(東京・上野公園)日本館1階 企画展示室、中央ホール
1875年6月1日に東京気象台(現在の気象庁)において、我が国の気象業務としての気象・地震観測が始まりました。
本展では、さまざまな自然現象を観測する手法やその歴史、これまで蓄積されてきた観測データから地球環境の様子やその変化が明らかになり、また防災・減災にも大きく貢献していることを紹介します。
展覧会詳細:https://www.kahaku.go.jp/event/2025/03observingearth/
国立科学博物館
住所:〒110-8718 東京都台東区上野公園7-20
公式サイト:https://www.kahaku.go.jp/
アクセス(GoogleMap):https://goo.gl/maps/zBoHtasXcNCq7FSt8
企画展「ドン・キホーテによろしく Chasing Windmills: Regards to Don Quixote」
会場:藝大アートプラザ
会期:2025年5月31日(土)〜7月13日(日)
ドン・キホーテはスペインの作家セルバンテスによる小説「ドン・キホーテ」の主人公です。騎士道物語の読みすぎ(!)で夢と現実の区別がつかなくなったドン・キホーテは、愛馬ロシナンテとともに遍歴の騎士になりきって冒険の旅に出かけます。ある日、ドン・キホーテは丘の上に巨人たちが立ち並ぶのを見かけ立ち向かいます。ですが、その巨人たちは夢の世界に生きるドン・キホーテの頭の中にだけ立ち現れた存在で、実は風車なのでした。
もしかするとアーティストはドン・キホーテなのかもしれません。あなただけに見えるたったひとつの世界は果たして虚構なのでしょうか? それとも私たちが現実だと思っている世界が実は幻なのでしょうか? 槍一つで風車に立ち向かったドン・キホーテのように、絶対に不可能だと思われることに立ち向かう行為は愚かなことなのでしょうか?
今回の企画では、制作という槍を携えて自分だけに見えている世界を追い続ける、アーティストの挑戦の数々をご紹介します。作家たちの声は果たしてドン・キホーテに届いているでしょうか?
藝大アートプラザ
住所:〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内
公式サイト:https://artplaza.geidai.ac.jp/
アクセス(GoogleMap):https://goo.gl/maps/w6T4HWuMghT2xfAX7
-2025年5月末更新-
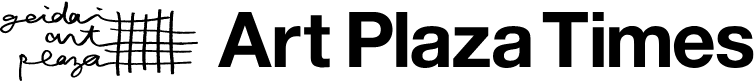

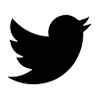 ツイートする
ツイートする
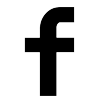 シェアする
シェアする
