先ごろ受賞者が発表された、第18回「藝大アートプラザ・アートアワード」(旧「藝大アートプラザ大賞」)。デジタル作品部門において「小学館賞」を受賞したのが、諏訪葵さん(写真)です。
受賞作「ガラス玉をひとつ」は、光と影が織りなす世界に迷い込んだような、あるいは目覚めのぼんやりとしたひと時のようなデジタルアート。
インスタレーションやデジタルアートというフィールドで活躍する諏訪さんに、作品づくりへの情熱や作家としての哲学をうかがいました。
作品の一場面。デジタル部門の受賞作品は、小学館メタバース「S-PACE(スペース)」にて公開中です。ぜひご覧ください。
アーカイブ映像を再構成した作品
――受賞作はどのようなきっかけで制作・出品なさったのでしょうか。
諏訪: 去年ぐらいから、まだ世に出せていない映像データのアーカイブ化をはじめました。学部では油画を専攻しましたが、普段はインスタレーション作品をつくるほうが多く、そうしたインスタレーション作品を映像として記録していこうという試みです。そうした取り組みの中で、アーカイブとして残していない映像データがSDカードにかなり溜まっていて、これらを世に出せる形で再構成したいという気持ちが原動力になって制作・出品しました。
――手に持ったガラス玉の後ろで、次々に背景が移り変わるのがおもしろいですね。
諏訪: 最近、入れ子状の作品を作ることが多くて、この「ガラス玉をひとつ」も同じ手法です。左手にガラス玉を乗せ、右手にカメラを持って撮影し、背景には2020年のコロナ禍における緊急事態宣言下で撮った映像を流しています。
背景の映像を制作した当時、私は修士課程に在籍しておりもともと個人的な活動が多かったので、集団生活がストップしてしまうような大変さはあまりなかったのですが、多くの人と同様に外に出られず、どこに行ってもパーティションで区切られるといった、もどかしい経験をしました。ガラス玉の後ろで流れている映像はそうした感覚を含めてを形にしたもので、無観客でのインスタレーション展示をしたいと考えて教授に相談し、紹介して頂いた群馬県桐生市にある山治織物工場という工場の跡地でインスタレーション作品の展示の様子を記録映像として撮影していく中で生じた映像作品です。

無意識と意識の狭間を映像に
――ガラス玉越しに映る世界は幻想的で、水晶をイメージさせるところから映像は少し呪術的・宗教的な印象もあります。何か特定の意味合いを持たせているのでしょうか。
諏訪: ガラス玉はインターネットで購入したもので、特別な意味合いは持たせていません。強いて言えばインターネット上で情報として存在したものを入手し、撮影する時に自分の眼の前に物質として存在し、また撮影することで映像という情報になる、ということを考えていました。ガラス玉を用いた作品は、他にもディスプレイにかざしながら撮影した写真作品もあります。映像ではなくガラス玉を使ってスチール撮影をしても、抽象画のような感じがして、私にはおもしろく感じられるんです。意味というより、ガラス玉を通すことによる世界のゆがみや、はっきり見えない部分にも表現の可能性が感じられると考えています。今までの作品の中でレンズやプリズム、フラスコなどを扱ってきたのも、そういった理由からです。
――審査員の一人は、この作品を「『懐かしさ』に似た感情」という言葉を使いながら読み解いていました。
諏訪: あのコメントはとても嬉しかったです。必ずしもすべてがきれいにクリアに映っていればいい、4Kや8Kといった超高画質であれば良いというわけでもないような気がしていて。
例えば、電車で寝てしまって目覚めた時の無意識と意識の狭間のような感覚、すごくぼんやりとした視界をガラス玉で表現したいと思っていました。そうしたテーマは、10年ほど前に「識閾(しきいき)」というタイトルでインスタレーション作品を制作した時からずっと私の中にあって、今も大きな興味は無意識と意識の狭間にあります。
「意識している」ことと「意識していない」ことの間に、私ははっきりとした境界線があるわけではないと思うんです。白昼夢みたいなこともあるだろうし、グラデーションの中で人間の認識が揺れ動き続けているということが、自分の作品づくりのベースにある気がしています。

自身の Instagramのタイムラインをガラス玉を通して撮影した写真作品。液晶画面上の情報とフィジカルな空間が混じり合い新たな情報になる。
科学の概念の中にいては「科学」はわからない
――アートとしての表現の裏側に、神経医学的なサイエンスの知見があるのですね。
諏訪: 考えてみると、科学に対する興味が小学生のころからありました。科学の中でも、特に化学への目覚めのような体験が小学5年生のときにあって。その時は、理科の先生がフラスコの中に液体を入れて、それを振った途端、液体の色がパッと鮮やかに変わったんです。その瞬間の美しさと驚きは、今もはっきりと覚えていますね。
その後もずっと化学が好きだったのですが、中学高校と進んでいくにつれて授業の内容が数学的になっていくように感じました。化学の現象、広く言えば自然現象の美しさを、数学的に記述していくのではなくて、その驚きをそのまま残しておくことのほうにより興味があるという感じでしょうか。
生物学者のレイチェル・カーソンが「センス・オブ・ワンダー」という言葉を残しているのですが、その言葉が表すことに私の感覚は近いように感じます。

――その感覚には、自然への畏怖や畏敬の念といったものも含まれるのでしょうか。
諏訪: そうですね、私が今ここに存在していること自体が、すごいことだと思うんです。何だかよくわからないけれど、みんな人間として生きて存在している。そういうことも含めて、この世界はすごいと感じます。その「すごい」をすべて分析して知り尽くしちゃうということもこれからは可能なのかもしれませんが、それよりもその「なんだか、すごい!」という感覚をつかまえて、アートとして表現できたら素敵なことだと思うんです。
――科学と芸術のどちらかを重要視するのではなくて、その間を自由に行き来するような感覚でしょうか。
諏訪: そうですね。もう少し深く考えてみると、科学の重要な要素に「再現性」があると思うのですが、仮に条件がすべて同じであったとしても、ある実験で得られた結果が次に繰り返した時も必ず起こるとどうして言えるのかは、厳密には断言できないのではないかと思うんです。
世の中にはまだ科学で解明できていないこともたくさんあるわけで、つまり「科学」という概念の中だけにいては「科学」の全容はわかりづらいのではないかと思います。私自身、科学の世界がとても好きだからこそ、科学という概念をより広くとらえて、アートとして表現していきたいと思っています。
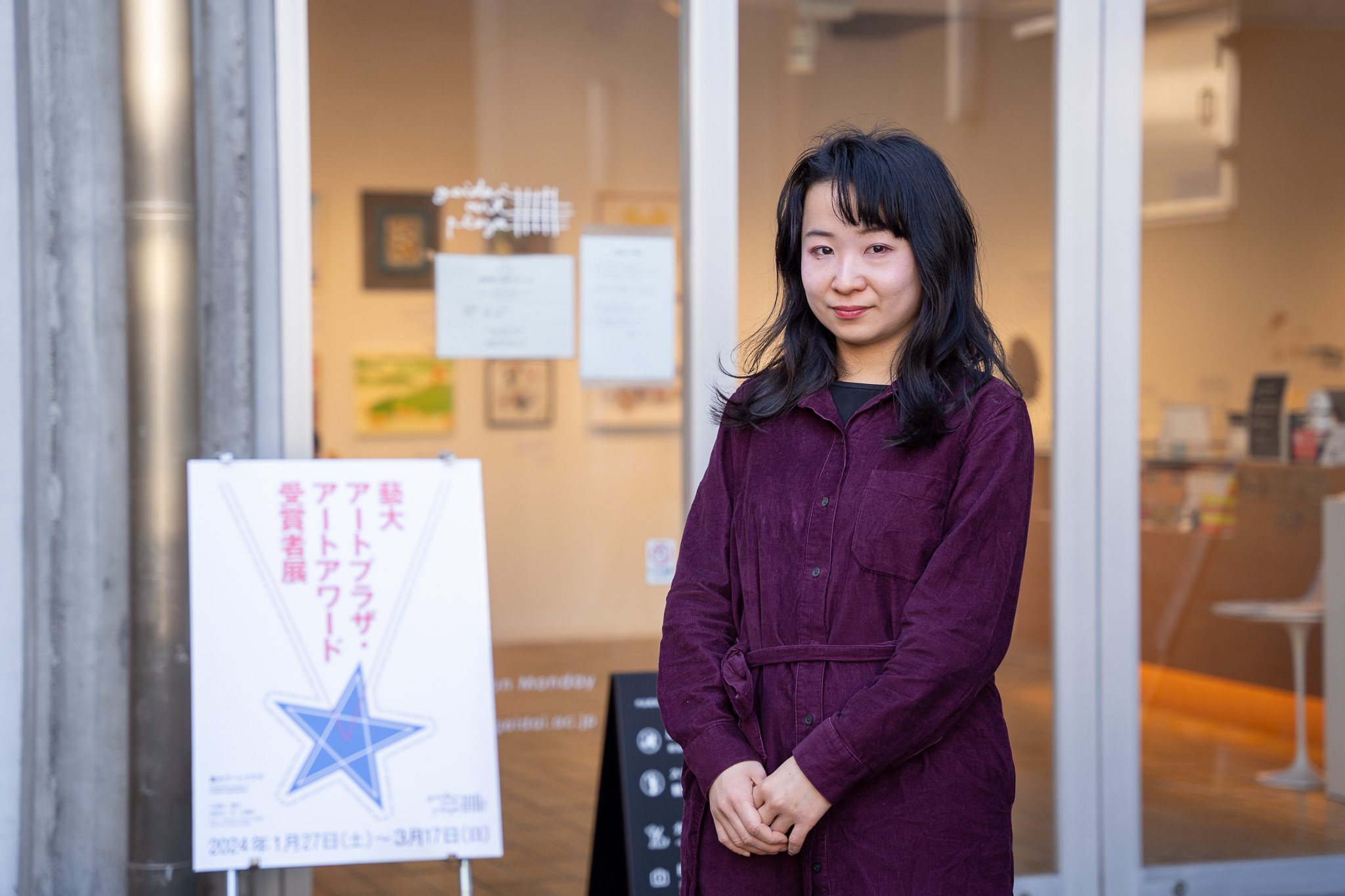
【諏訪 葵(すわ あおい)】
1991年 東京生まれ
東京藝術大学大学院 美術研究科博士課程 在学中
インスタレーション、平面、映像を中心に様々なメディアを行き来しながら作品を制作している。液体の色が変化する化学反応を見た感覚が原体験となり、現在は科学的な現象や概念と自己の知覚や感性との関わりによって生まれる「場」や「接面」に着目している。
近年の主な賞歴、展示など
2024 諏訪葵 個展「まだ見ぬ識閾 平面世界とインスタレーションの並行 」ターナーギャラリー(東京、南長崎)
2024 「Unfelt Threshold ― まだ見ぬ識閾」Käte Hamburger Kolleg(アーヘン、ドイツ)
2023 東京ビジネスデザインアワード テーマ賞
2023 令和5年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業 発表支援
2022 第二回KYOBASHI ART WALL奨励賞
2022 グッドデザイン・ニューホープ賞 入選
2019 NONIO ART WAVE AWARD 2019 準グランプリ
その他、科学と芸術の関わり合う領域への興味から学際的な活動にも注力しており、科学者とアーティストが関わり合う学際的なプログラム「ファンダメンタルズ」に2023年度アーティストとして参加。
Instagram:https://www.instagram.com/aoi.suwa/


 ツイートする
ツイートする
 シェアする
シェアする
