第19回「藝大アートプラザ・アートアワード」の準大賞を獲得した三浦潮音さん(美術学部工芸科素材造形ガラス専攻)。受賞作「Horse」(写真下)は、ガラスの精緻なたたずまいと異素材の組み合わせから成るユニークで温かみのある造形が印象的です。
お話を通して、ガラスという素材の性質や魅力を探求しながら創作に取り組むひたむきな姿勢が見えました。

日比野克彦・東京藝大学長をはじめとする審査員の講評はこちらからご覧ください。
人のためにつくり続けたい
――今回の受賞作「Horse」は、どのようなコンセプトで制作されたのですか。
三浦 「服を着替えるように、インテリアも着替えられるようにしたい」という想いから制作に至りました。このオブジェは1セット分なのですが、他に付け替えできる馬や足も制作しているので、買い足して付け替えていただければ、季節や気分によって変化を楽しむことができます。
私はお着物が好きなんです。着物は帯や小物といったパーツが多くて、季節や出かける場所によって柄などを考えますが、会う相手によって替えることもありました。「Horse」も玄関などに置いていただき、お客様に合わせてパーツを替えてもてなすこともできます。そういったおもてなしの心を作品に込め、プラスのエネルギーを生み出したいと思い、制作しました。

――馬の形が印象的です。
三浦 動植物のモチーフは広く好まれる傾向にあると思いましたので、自分がつくれるもので、皆さんが楽しい気分になれるものを探しました。その中で、日本では縁起の良い動物とされ、ヨーロッパでは馬蹄が幸福を示すなど、広く吉祥の意味を持つ生き物である馬が思い浮かんだのです。
私は人のために作品をつくり続けていきたいと思っていて、見ていて楽しい気持ちになれるもの、疲れている人の気持ちに寄り添うことができるものということで馬を選びました。

――今までつくっていた作品も動物モチーフなのでしょうか。
三浦 いろいろな作品をつくっているのですが、キャラクターや動植物などはあまり手がけていなかったので、今回は私としては新機軸の制作でした。
過去には、ガラスの心臓をコアガラスという技法で製作し、真空パックした作品を発表しました。ガラスの心臓を覆っているパックには「Life won’t wait.」という文字が書かれています。普段普通に過ごしていると忘れてしまいますが、いのちは私を待ってくれません。忘れてしまわぬように自戒の意味を込めて作品を作りました。
また、ガラスの風鈴も製作しました。風鈴は元来、日本においては災いから身を守る為の魔除けとしての役割があります。そのため、この作品では、心を意味する核と周囲に巡らせた透明の防御壁で、現代社会の魔除けの意味を込めています。
このように作品制作時には、頭の中で思考を巡らせてから制作に入ります。


探求しながら形づくる
――「Horse」も含め、作品全般の制作過程について、教えていただけますか。
三浦 ガラス工芸の製法は、熱いガラスを吹くホットワーク、水で冷やして加工するコールドワーク、窯にガラスを詰めた型を入れてつくるキルンワークの三つに大別することができます。このうちホットワークは溶かすので艶が出て表面が軟らかくなり、コールドワークは切り子やステンドグラスのような細かい細工が可能で、キルンワークはざらざらした質感やマットな印象にすることができます。
「Horse」は、馬の部分はキルンワークでつくりました。まず粘土造形で馬をつくり、シリコンで型を取って蝋を流し込むと蝋に置き換わった馬ができます。そこに石膏を流し込んで脱蝋すると馬形の穴が空いた石膏ができます。そこにガラスを詰めて窯で焚きました。足はホットワークでつくっています。
――お持ちいただいたパーツは、形は同じながら、雰囲気が異なりますね。
三浦 馬の部分は全てキルンワーク、足はホットワークとキルンワークで制作しました。ホットワークで使う色ガラスをキルンワークで使って濃い色を出すなど、普通はあまりやらないような挑戦も普段からしています。透明のガラスと色ガラスは膨張係数などが異なるので、そういったことも計算しながら試みました。

ガラスという素材の不思議
――藝大の工芸科の中で、ガラスを専攻したのはなぜでしょうか。
三浦 工芸分野で扱う素材を、加工せずにそのまま机に並べてみたときに、一番に目を惹く素材はガラスなのではないのかという仮説が自分の中にありました。本能なのか、人も人以外の動物も、透明でキラキラしているものには惹かれる傾向があるように思います。
私の中には、(ガラスは)なぜそれだけで評価されるのだろうという疑問がありました。そういう意味でガラスは素材として不思議だと思った事が、選択した理由です。
――ご自身がガラスを「きれい」だと感じたのではなくて、「人がきれいだと感じるのはなぜだろう」と探求したいと思ったんですか。面白いですね。
三浦 はい。他にガラスを専攻している知人や友人に話を聞くと、「キラキラしていて綺麗だからガラスを選んだ」という理由が一番多く返ってきます。それを聞いて私は、「キラキラしている=綺麗」と思う理由はなんなのだろうと疑問を持ち始めました。
あとは、ものづくりとして同素材での継ぎ接ぎはできれば避けたいなという気持ちがあり、何度でも形を変えられるガラスの性質が私の性格にも合っているのかなと思います。
――ガラスを専攻して、なぜ人がガラスに惹かれるのか分かりましたか?
三浦 まだはっきりとは分かっていません。ただ、今回のような作品とは別に、ガラスリングやイヤーカフなども作っているのですが、ガラスのアクセサリーは不透明なものより透明なものの方が好まれますし、クリアな方が指や耳を美しく見せてくれます。つまり、ガラスの透明さは一緒にあるものをきれいに見せたり、引き立ててくれるのだと考えています。
あとは太陽光を透過してガラスのアクセサリーがキラキラと光る時、見ている人も身に着けている人も、ポジティブな感情になることで、プラスのエネルギーを生み出す素材なのだと思っています。

アートとは、人にポジティブなエネルギーを与えられるもの
――三浦さんにとって、アートとはどのようなものでしょうか。
三浦 人にポジティブなエネルギーを与えられるもの、だと思っています。例えば落ち込んでいる時にカモミールティーを飲んだり、青空や海などを見たりすると気持ちが落ち着くことがありますよね。アートもそういった存在であってほしいと思っていて、ポジティブなエネルギーの受け渡しをするための方法を模索しています。
賞をいただいた「Horse」も、足を付け替えるなどして楽しんだり、いろいろ遊んでいただけたら嬉しいですね。
――「付け替えられる」という点を特に重視しているのはなぜでしょうか。
三浦 それは多分、幼少時の経験などに由来しますね。私は、小学校3年生のある時期までは子どもが好む色が好きで、ピンクなどの色の服を着ていたのですが、あるとき「大人になっても、使えるような服を着たい」と思うようになり、4年生からは茶色などのナチュラルな服を着るようになりました。その時から、大人になっても使えるもの、飽きないもの、一生持っていたいものを好むようになったのです。
いわば、「単に消費されるだけのもの」に疑問を感じるようになったのですが、それは根本的に変わっていないと思います。「Horse」も足を固めて一つのオブジェとして固定させるのではなくて、付け替えるということで永続性を持たせたいという考えに基づいています。
――作品の多様さや探求心、コンセプトや思索の深さから、さまざまな軸がありそうです。
三浦 私の中では重視していることがいろいろあって、「Horse」のように人のためになりうるものをつくる、風鈴の作品のようにテーマに与して歴史を辿る、日常でこんなものがあったらいいな、を発見して派生させる、理由はわからないけれど、直感的に良いと思ったデザインのものを作る、といった複数の軸があります。

抽象的なものも具象に近いものも、使うためのものもつくりますし、今後は大きな作品もつくりたいのですが、自己満足になりたくないという思いは一貫しています。アッサンブラージュなども好きなので、自分の感覚を生かし、いろいろな軸が重なる部分を探りながら探求していきたいですね。

【三浦 潮音(みうら しおね)】
2001 9月22日 東京都世田谷区生まれ
2017 東京都立総合芸術高等学校美術科油彩画専攻入学。在学中、中央展に選出
2020 二人展「たしかに、そこに」
2022 東京藝術大学美術学部工芸科入学
現在、東京藝術大学 美術学部3年 工芸科素材造形(ガラス)在籍
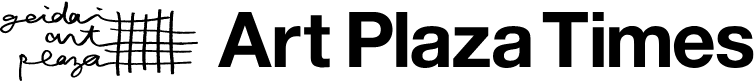

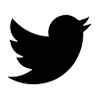 ツイートする
ツイートする
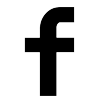 シェアする
シェアする