「ART PLAZA TIMES」では、小説家・長者町岬氏による対話企画「日本美術 近代化の蹉跌」をスタートします。長者町氏は東京藝術大学を卒業後、東京国立近代美術館の研究員として数々の展覧会を企画した後、東京都庭園美術館の館長などを歴任し、その後小説家に転身した異色の経歴の持ち主。
タイトルにある「蹉跌(さてつ)」とは、「物事がうまく進まず、しくじること」や「挫折」を意味する言葉で、日本美術には近代化によってもたらされた大きな「蹉跌」があったと、氏は考えています。
第1回では、友禅作家として重要無形文化財(人間国宝)に指定されている森口邦彦氏との対話の様子を、ご紹介します。
長者町岬(ちょうじゃまち みさき)
1950年、東京幡ヶ谷生まれ。本名、樋田豊次郎。東京藝術大学で美術史を学び、展覧会企画および芸術研究の道に進む。東京国立近代美術館の研究員として数々の展覧会を企画し、意欲的な工芸論を展開。その後、秋田公立美術大学の学長・理事長、東京都庭園美術館の館長を歴任した後、小説家に転身。小説『アフリカの女』(現代企画室)、『台湾航路』(田畑書店)を上梓している。
森口邦彦(もりぐち くにひこ)
1941年、京都市生まれ。友禅作家であり人間国宝であった故・森口華弘氏の次男として生まれ、京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)日本画科を卒業後、パリ国立高等装飾美術学校に留学し、グラフィックデザインを学び卒業。帰国後、華弘氏の弟子となり友禅を学び、2007年(平成19年)に父と同じく人間国宝となる。友禅作家として、伝統的な友禅の技法を用いながら既成の概念を超えた斬新なデザインを世界に向けて生み出しつづけてきた。
工芸の拠りどころ
高橋明彦(司会・金沢美術工芸大学教授) 最初に少々僭越なんですけれども、今日「対話」されるお二人を私の方から紹介させていただきます。私は金沢美術工芸大学教授の高橋明彦です。専門は哲学史です。
今回の企画は、長者町岬さんのたっての希望で、森口邦彦さんをお招きして実現しました。森口さん、京都からおいでいただきましてありがとうございます。お二人の略歴をいただいておりますので、これを紹介させていただきます。
まず森口邦彦さんは染色家で重要無形文化財「友禅」の技術保持者いわゆる人間国宝でいらっしゃいます。京都市立美術大学の日本画科を卒業後、フランス政府給費留学生として渡仏されまして、パリの国立高等装飾美術学校でも学ばれました。
伝統工芸の分野を歩まれ、数々の賞を受けて作家としての地歩を築かれた方ですが、同時にパリ装飾美術館の館長とも深い親交を結び、京都国立近代美術館で「フランスのタピスリー展」が開催されたときには、そのキューレーションを担当されました。また、「日本の染織展」などのコーディーネーターとして国際交流にも尽力されてきました。このように世界的な視野で活動されてきたご経歴から、本日の「対話」には、西洋芸術の視点から見た日本の伝統工芸の状況が浮き彫りにされるのではないかと期待されます。
二〇一四年には、三越百貨店のショッピングバッグを五十七年ぶりにリニューアルする「実り」をデザインして、着物以外の分野にも積極的に挑戦されています。二〇二〇年には、友禅作家としての集大成となる「森口邦彦 友禅/デザイン―交差する自由へのまなざし」展が京都国立近代美術館で開催されました。今年の三月まで本学の客員教授も務められました。
一方、長者町岬さんですが、この装飾研究会の代表でもあります。本名は樋田豊次郎さんです。三年前から小説を書きはじめて、長者町岬というペンネームを使われています。今回は長者町岬で通すという方針なんですが、僕も長者町さんと言ってみたり、樋田さんと言ってみたりで一貫しなくて申し訳ございませんが、その辺の事情も含めてご紹介します。
樋田さんは東京藝術大学を卒業後、東京国立近代美術館工芸館の学芸員としてずっと日本工芸を研究されてきました。同時に秋田公立美術大学の学長兼理事長等々にも就いていることもあって、我々の属している美術大学の現状もよくご存じです。森口さんと同じく、今年の三月まで本学の客員教授も務められました。その縁で装飾研究会が出来ました。
研究者としての樋田さんは、「工芸」という領域を、日本の近代の問題として捉えているということが、私なんかの外部から見た者の興味を引くところでもあるわけです。略歴の「研究の動機と目的」という部分で、樋田さんは「日本の文化構造を解き明かす方法として工芸に注目した。日本工芸が外来の東洋美術や西洋美術から受けた影響、そしてその影響に対する日本工芸の反応に関心をもってきた。それらを美術史としてではなく、日本人の芸術観として理解することが最終的な目的だ」と書いています。それだからでしょうか、最近その美術史に限界を感じて表現者に転身され、名前も長者町岬に変えたそうです。人生を楽しんでいるようで、うらやましいかぎりです。それでは長者町さん、この後よろしくお願いします。
長者町 高橋先生、ありがとうございます。いまも話がありましたように、今回の企画はぜひ森口さんと対話したいと私がお願いして実現したものです。そんなわけで、最初に私の方からこの企画の目的を話させてください。
1
私は長い間、美術の歴史を研究してきました。とくに幕末の開国から現在までの工芸史が専門でした。そんないわば美術史漬けの人生を送ってきた私から見ると、十九世紀後半以降の日本美術は、「西洋化」と「日本化」との二本立てでした。
西洋化のほうの基本原理にあったのは、西洋芸術の輸入によって日本を近代国家にしようとする「近代主義(モダニズム)」です。明治初期には工部省がイタリア人美術家を招聘して、明治中期以降は美術家自身のあいつぐ留学によって、西洋芸術の輸入がおこなわれています。
ところが華々しいスタートを切った美術の近代主義でしたが、それは現在までの約一五〇年間のあいだに、二回「拒否」を突きつけられています。拒否を表明したのは、いうまでもなく美術の「日本化」を標榜する側でした。そしていま、三回目の拒否によって、美術の近代主義が果たしてきた役割そのものに懐疑の目が向けられています。
こうした拒否の表明は、あくまでも美術という領域のなかでの出来事でしたが、大づかみにいえば、明治維新という「革命」にたいする「反革命」のようなものだったのでしょうか? そうであれば、「西洋化」側に拒否を突きつけた「日本化」側の目的は、比較的容易に理解することができるでしょう。しかし彼らの目的は、たとえば大革命後のフランス共和制が何度も経験してきた反革命運動における王制や帝制への復帰とはちがっていました。
そのため、日本美術に起きた西洋化と日本化の対立には分かりにくいところがあります。そもそもなんで対立していたのか、その理由さえあいまいです。互いに相手を排斥していたというほどのこともありません。それぞれが異なる主義主張を掲げて、棲み分けをしていたに過ぎないともいえます。
2
美術の「日本化」側の基本原理にあったのは、自国に残る文化資源の活用によって日本を欧米と肩を並べる国にしようとする「国家主義(ナショナリズム)」です。十九世紀末から文部省、農商務省、内務省、宮内省の官僚たちは日本美術の体系化と、それによる日本美術の価値創出に着手しています。
内務省は一八九七年(明治三〇年)に古社寺保存法を制定し、国宝の指定をはじめます。農商務省は一九〇一年(明治三四年)に、官製の美術史として「稿本日本帝国美術略史」を出版しますが、これは前年のパリ万博参加に際し、日本には美術の歴史があることを西洋人に誇示する目的で編纂された「Histoire de l’art du Japon」の日本語版でした。
さて、ここで工芸が登場するのですが、一回目に近代主義が拒否されたとき、その象徴として主役扱いされていたのが工芸でした。たとえば文部省の事務官出身で、帝国博物館総長、貴族院議員に上り詰めていた九鬼隆一は、一八九三年のシカゴ万博参加に際して、全国の工芸家たちに日本の文化遺産を出品作に盛り込むよう、ことこまかく指示しています。日本画にも同じ役割が期待されたことでしょう。しかし、いかんせん当時の日本画は海外で不評でした。
これらは官製の国家主義です。これと同時に、民間の国家主義もありました。明治の民衆も、日本を文化の一等国にしたいという夢を見たわけです。当時の民衆がそれをどこまで自覚していたかは分かりませんが、その夢は空気のなかで生きている我々が空気を意識していないように、いつのまにか民衆を虜にしていました。
3
官と民に拒否を突きつけられたのは、主として西洋画家と西洋彫刻家でした。彼らの近代主義は、どうなったか? 彼らは、まずは自分たちの領土確保に向かいました。たとえば一八八七年(明治二〇年)に東京美術学校が設立されたとき、当時の学校方針は国家主義だったので、そこに西洋画科はありませんでした。しかし方針が変わって、九年後にその設置が認められると、そこには日本中から洋画志望の学生が集まってきました。また一九〇七年(明治四〇年)に文部省美術展覧会が開設されると、その第二部(西洋画)は洋画家の登竜門となります。この現象は現在の東京芸術大学油画科の入試倍率、そして日展洋画部門の入選率にまで受け継がれます。
これは一種のセクショナリズムです。西洋画、日本画、彫刻、工芸、建築、デザインといった各分野が独立し、互いに干渉することなく、美術大学、展覧会、美術団体を運営するという、今日の日本美術界の原型ができあがったわけです。
これに拍車をかけたのは、画家たちの留学が、西洋絵画にそなわる技術と様式の習得に終始したことです。もちろん当事者たちは、西洋絵画の精神を掴かみとる意気込みで出かけていったにちがいありません。しかし、そうはいきませんでした。数年間フランスやイタリアに滞在しただけで、ギリシャ以来の西洋芸術の精神を掴むなんて、土台無理な話でした。そんなこと奇跡でも起きなければできるはずがありません。
そのため西洋画家たちの近代主義は、当初彼らが期待したように、日本の美術界に地殻変動を起こし、日本人に江戸の芸術観と訣別させることができませんでした。
工芸家も美術の近代主義に気づいてはいたでしょうが、文展に工芸部門が設置されなかったことで、彼らは自前の領土さえ確保できませんでした。大正二年(一九一三年)に農商務省図案及び応用作品展が開設されると、工芸家たちはそこに西洋芸術の意匠をまとった家具や手工業製品を出すのが精一杯でした。
明治初期に、日本の銅器や陶磁器、そして竹細工や扇子のような小間物が、西洋人のオリエンタリズムを刺激する輸出用工業製品として人気を博しましたが、そういう工芸認識は、昭和二年(一九二七年)に帝国美術院展覧会(文展の後身)に、工芸の出品が認められるようになるまでたいして変わらなかったのです。
国家主義を基本政策とした官僚たちにすれば、西洋画家や西洋彫刻家の近代主義は、和魂洋才の「洋才」を追うばかりで、「和魂」をブレイクスルー(破壊的創造)させる力がないと感じていたことでしょう。
4
ちょっと寄り道しますが、東京美術学校の西洋画科には、日本中だけでなく、当時日本の植民地だった朝鮮、台湾、満州からも、画学生が内地留学してきました。フランスに留学した日本人がもち帰った西洋絵画の技法と様式を、今度は東京で植民地の人たちが学んだのです。模倣の模倣がはじまるんですね。これは結局、日本も含めて、遅れて開化をはじめた極東の小国が西洋文化を輸入するときの宿命だったんでしょう。
それにしても、日本の植民地だった国では、模倣の連鎖から抜け出すのに大変な苦労をしています。いまでも韓国に行くと、現地の研究者・関係者からは、植民地期の影響をめぐる厳しい評価や指摘に接することがあります。そんな状況から目を背けたくなかったので、私は「台湾航路――同化政策にあらがった陳澄波と藤島武二」という小説を書きました。
私が大学に入ったのは一九七〇年ですが、その頃でも日本各地の工芸家の子弟が東京芸大をはじめ、東京の美術大学にやってきて、西洋の現代絵画、彫刻、デザインを学んで、それを地元にもち帰って、家業である工芸制作に組み込むことがおこなわれていました。明治の画家たちの洋行をスケールダウンした国内留学がおこなわれていたわけです。
そのなかに、私と年が一歳かそこらしか違わない十五代の樂吉左衛門がいました。あるとき、なんの仕事だったのかは忘れましたが、多治見に行ったとき、旅館で彼と相部屋になったことがあります。私は楽茶碗の知識がなく、それが炭で焼成されることも分かってませんでした。樂さんは呆れてました。
話が西洋芸術におよんだとき、東京芸大の彫刻科を出ていた彼に、私は西洋彫刻の空間把握と楽茶碗の造形との関係を訊いてしまいました。樂さんは当然そういうことに苦心惨憺されていたんでしょうね。ちょっと険悪な空気になってしまった苦い思い出があります。たとえ美術の近代主義が拒否されなかったにしても、極東の美術家は西洋芸術の精神を掴むことの困難さを感じてきたのでしょう。
5
美術の近代主義に二回目の拒否を突きつけたのは、戦後の文部官僚たちでした。彼らは戦争に負けた日本人に自尊心を取り戻させる目的で、つぎのような論を立てています。
およそ国家が自民族の優れた文化的遺産の保護に万全を期することは、決して偏狭な民族主義に基づくものではなく、われわれにつづく世代に対し、又ひいては世界人類に対して負わされたわれわれの崇高な義務ともいえるのである。何となれば、われわれに継承された多くの文化的遺産は、その創造、その選択において、先人の創造と伝承により培養され育成されたところの超人格的価値の結晶ともいえるからである。
(「文化財要覧、昭和二六年版、文化財保護委員会」より)
この論理が、民衆の欧米を見る目から国家主義を払拭しました。その代わりに、民衆の国家主義の根底に眠っていた愛国的心情を呼び覚まします。いわば、国家主義(ナショナリズム)を愛国心(パトリオティズム)に変容させたわけです。こういう論理を官僚が発案したこと、そして民衆がそれに共鳴したことは、日本人の智恵でした。
民衆の愛国的心情を根拠にして、文部省は国宝などの有形文化財と並ぶ、無形文化財という概念を創出し、それにもとづいて重要無形文化財技術保持者いわゆる人間国宝の指定をはじめます。そうした保持者の作品展示が、現在までつづく日本伝統工芸展という公募展の起源です。
6
いよいよ三回目の拒否です。これについては、森口さんとの対話のなかで話をしたほうが具体的でよいでしょう。ですが前もってひとこと言及すれば、三回目の拒否を発動したのは、政府や文部省のような組織ではなく、かといって官僚や民衆のような人間でもなく、工芸という芸術それ自体の変容でした。
これまで工芸は、国家主義、愛国的心情を拠りどころにしてきました。いってみれば、外部の基本原理にもとづいて(あるいは巻き込まれて)、近代主義を拒否する象徴となってきました。ところが最近になって、工芸は近代主義に直接異議を申し立てる芸術に変容しつつあるようなのです。
これには多少説明が要るでしょう。まず工芸という言葉(概念)ですが、これは明治になってからの発明品でした。近代になってそんな言葉が必要とされたのは、殖産興業に役立つ工業製品を総称する概念がなかったからです。ですから最初のうち、工芸は工業と見分けのつかない言葉でした。シカゴ万博参加の際、九鬼が工芸にあれこれ注文をつけたのも、工芸品が有力な輸出工業製品と位置づけられていたからにほかなりません。工芸という言葉(概念)は、その誕生のときから国家主義と親和性が高かったのです。
戦後、工芸の拠りどころは愛国的心情となりましたが、その愛国的心情も、いまでは工芸に救済を求めようとする人たちの心には刺さらなくなっています。「工芸はかつての工芸ならず」、といったところです。工芸は自分ほんらいの姿を取り戻すことで、美術の近代主義が残した弊害を拒否しはじめているように思われます。
7
では、工芸のほんらいの姿とは、どのようなものなのでしょうか? それを知るには、明治以前の工芸を呼び戻さなければなりません。まず、名称です。工芸という言葉を使ってしまうと、近代の工芸概念を連想させるので、これはもう止めたほうがいいでしょう。
代わりに、私は「装飾」という言葉の使用を提案します。私はこれを、アール・デコにかんする本を書いていたときに見つけました。共和制の時代を築いたフランスのブルジョワ階級が、自分たちの集団にふさわしい芸術を、「Art Décoratif」(装飾芸術)という言葉で総称していたのです。
装飾にはキッチュな印象がありますが、そのほこりを払って、新しい命を吹き込めないかと模索しています。装飾研究会を立ち上げた目的にも、こうした提案がありました。
では、明治以前の装飾(工芸)とはどんなものだったのでしょうか。これからの装飾(工芸)を考えるにしても、それを手がかりとするしかありません。私はこの作業を、理論的試みとしてではなく、現実の工芸家がどう生きてきたのかを知ることによってやってみようと思います。いわば一種の人間論として装飾を捉えたいのです。いま役目を終えようとしている近代の工芸を、閉塞感から解放して、装飾につなげようと目論んでいます。
それでは森口さん、よろしくお願いします。
装飾じゃなくて和様
森口 今日はお招きいただきありがとうございます。六月一二日に樋田さんが、これは長者町さんとしてはなくてですね、私の家に訪ねてこられました。四時間議論をさせていただいたのですが、それがこういう風に繋がったと思います。
しかし四時間もお話しましたが、なぜ「装飾」なのかという点で違和感があります。僕は理屈でものはつくれないと思っているので、こういう企画にかかわっていいのかなと思いながらも、長者町さんは、やっぱりなにか日本の工芸の閉塞感をぶち破ろうとしておられるような、そういう貴重な考えをお持ちなので、そこに積極的な意味を感じ、今日ここへ来ることを承諾いたしました。決して装飾という言葉に、共感しているわけでもなく、いまだになにかちがうんじゃないかと思っています。
長者町 先日、佐和隆研の論文のコピーを送ってくださりましたね。
森口 あの論文には、僕が友禅の技術を勉強するようになったきっかけというか、ベースをつくってくれた日本美術の様式的展開と特質が書いてあります。あれが僕の出発点のような気がします。あの論文の最後に、僕たちものをつくる学生にたいするエールが出てくるんです。それが僕ものすごく好きですね。僕はもう胸が熱くなるような思いをした。それが僕の美術史にたいする興味の原点なので、長者町さんにもわかっていただきたいと思って送りました。
長者町 その論文になにを読み取ったのですか?
森口 僕は「和様」に引かれました。長者町さんがいう「装飾」を、僕の歴史の知識のなかで名づけるとすれば、「和様」、あの唐様とは違う和様ということなのかなと思います。
つまり日本が誇る宇治平等院の扉絵にはじまる和様が、平安時代から展開してきて、信貴山縁起絵巻や鳥獣戯画を経て、宗達から光琳に至るという風な感じの和様の美です。これをもう一度、日本画とか洋画とか工芸とか、そういう枠組みを取り払って考えてもいいのではないかと思います。それが、この閉塞感のある時代を打ち破ってつぎの時代をつくることになるのかなと僕は思いましたのでここに来てみました。それと、 佐和先生が論文で美術は「様式」ではないと書かれていたことも忘れがたいです。先生は僕たち学生に、かたちを写すなと戒めてくださっているようでした。
ところで、僕は最初に長者町さんに会ったのはパリの装飾美術館だったと記憶しております。
装飾美術館
長者町 そうでしたっけ。
森口 長者町さんは装飾美術館で勉強しておられたんですね。
長者町 一九八五年の一〇月か一一月だったと思うんですが、私はパリで森口さんとはじめて会いました。ただし、場所はパレロワイヤルの回廊にある喫茶店で、先生にコーヒーをごちそうしてもらったことしか覚えていません。装飾美術館でしたっけ?
森口 そうでしたよ。僕がそのころお世話になっていたガエタン・ピコン――彼はアンドレ・マルローの右腕で、ポンピドゥーセンターの生みの親なんですけども――その奥さんが装飾美術館にある図書館の館長をしておられました。僕はパリで個展があり、その折り彼女に会いに行ったのですが、そこに樋田さんがいたんです。
長者町 それにしても一九八五年ですから四十年前、大昔ですね。
森口 朝日新聞で去年の十二月に自分自身のことを語る連載があったんです。そのとき朝日は、この装飾美術館のことを装飾芸術美術館と呼んでいました。あなたの「装飾」論が、僕に複雑な思いを起こさせています。「装飾芸術」といえば装飾の格が上がるようですし、しかし装飾が近代の芸術至上主義にすり寄っているようにも聞こえますしね。
その連載では、館長のフランソワ・マテイの話もしました。もう亡くなりましたが、彼は装飾美術館の館長でありながら、現代美術のホックニーや、バルテュス、イッセイミヤケ、それから建築の展覧会を開催していました。僕にとってそんな装飾美術館が理想的に見えていました。
長者町 私は森口さんとは違って、研修生みたいなスタージュという立場で、半年間あそこにいました。その立場から見ると、装飾美術館は美術界のヒエラルキーのなかで孤軍奮闘しているなと感じました。なにしろあの美術館は、大きなルーブル宮殿のほんの一角を占めていたにすぎません。上から見ると凹の字型をしたルーブル宮殿の右上先端です。あとの一部はフランス大蔵省が使ってましたが、ほとんどの部分はルーブル美術館でした。
当時すでに、ルーブル美術館の大改装計画が進んでいて、中庭にピラミッド型の入口ができると書いた説明看板が立てられていました。それを見て、私が所属していた東京国立近代美術館の工芸館と本館との、力の格差を思い出したことを覚えています。
装飾美術館の学芸員たちも負けじと意気軒昂で、展示のハイライトにアール・デコをもってきたり、館のキャッチコピーに「ルーブル」を避けて、「リヴォリ通り一〇七番地」という住所表記を使ってました。ちなみに、当時はまだアール・デコという用語が定着していなくて、「一九二〇年代様式」という用語が使われていましたが……。
森口 装飾美術館の建物はすべて国のものです。それから従業員もすべて国家公務員です。だけど運営しているのは装飾美術組合という民間組織なので、それもあってマテイ館長は好きなことやれたんでしょう。僕が一九七五年に京近美でフランスのタペストリー展を開きたいと依頼したときも、マテイ館長はとても喜んでくれました。彼はそのとき来日して、京博の裏にある大衆食堂のショーウインドウで蝋づくりの食品見本を見つけてとても面白がっていました。
蝋の食品見本という低いレベルにしか扱われてないものにものすごく感動してですね、これこそ日本だというので、その食品見本の展覧会を装飾美術館で開催しています。好き放題やってましたが、その後ポンピドゥー大統領との行き違いがあって、最後は寂しく装飾美術館を去りましたけどね。
マテイが好き放題をやってた美術館に、長者町さんは短期留学されてたんですね。長者町(樋田)さんの背景もそこで出来上がったのかなと、いま思いました。
長者町 マテイはナポレオン三世時代の体質をもつ美術館、つまり共和制の政治にたいして帝政回帰しようとする復古的体質が残存する美術館にいたわけですね。それでも近代的な芸術を求めていたところに、森口さんは感銘を受けたのでしょう。
それじゃあ私も、反共和制的な体質と闘わなければいけませんね。でも、具体的にはなにと闘えばいいんでしょうか。日本の美術館に根づよい役人の事なかれ主義? 絵画や彫刻よりも工芸を下に見る世間の本音? それとも、美術展の評価を質よりも量に求めるブロックバスター(大量観客動員)依存症?
いや、もう職を辞した私には、そんなことはどうでもいいことばかり。それよりも近代の工芸家(フランス風にいえば装飾芸術家)が、大衆消費社会の商品生産というイデオロギーにからめとられて、それによって自らのアイデンティティを深めるチャンスを失っていったことの方が気にかかります。いってみれば、私の闘うべき相手は、芸術家の信念をくじく大衆社会の欲望なのかもしれません。
森口 マテイさんはね、僕がパリでまだ学生だった頃に知り合って、最後までお付き合いしていただいた方です。やっぱりあの自由さには引かれましたね。
長者町 私もあの美術館には思い出がたっぷりあります。ただ、あそこで見た装飾は、ゴシック、ルネッサンス、ロココの時代から継承されてきた調度品の華やかな「様式」の変遷でした。マテイはそういう展示を組み替えたかったんでしょうね。
日本の工芸家にしても、東京美術学校の鋳金科教授だった津田信夫は、アール・デコの登場で有名になった一九二五年の博覧会で国際審査員を務めていますから、装飾美術館の「様式」展示を見ているはずです。ところがなんの躊躇もなく、アール・デコを最新流行の形態として日本に持ち帰ってきて、後輩に伝授しています。当時は様式の受容を重視する傾向が強かったのでしょう。日本でも工芸は、それほどまでに様式の産物という考え方に支配されていたということでしょうか。
森口さんの場合はいかがでしたか? 森口さんはパリ留学によって、家業である友禅染のブレイクスルーを意図していたと、私には見えるんですが。
なぜ着物をつくるのか
森口 友禅染のブレイクスルーなぞ、思いもよらぬ気恥ずかしい表現ですが、そのような気持ちは留学する前から芽生えてはいたと思います。
東京芸術大学に入って右側に行くと食堂がありますね。その奥に石炭小屋が昔あったのですが、その隣に西田正秋先生の研究室がありました。僕は西田先生の美術解剖学の講義を、テンプラ学生として聴講していました。西田先生の人体美学が僕を誕生させ、独自な友禅模様を生みださせたといっても過言ではありません。余談ながら、西田先生のことを僕に教えてくれたのは、東京美術学校の日本画出身で、東京国立近代美術館工芸館の初代工芸課長に就いた杉原信彦さんでした。
長者町 人体美学のどこに引かれたんですか?
森口 友禅の着物は、道具としての側面があまりにも無視されていると感じます。なんていうかな、華やかな晴れの日の正装として、吉祥文などが染められるのが通例となっていますが、僕は女性が着物を纏ったときに、一本の直線はどんな角度をしていたら、三次元のスパイラル(渦巻)として完成するのかと考えて、模様をつくってきました。それで、晩年の西田先生に教えを請うたのです。
売れるか売れないかなんて、もうそれはまったく無視して、女性の身体や着装したときの所作を美しくするために、人体美学を学びました。
長者町 着物の模様は、着装したときに生きてくるということですね。
森口 そうです。もっともこれには注釈が必要です。絣という織物を例にとると、金沢美術工芸大学の足立真美先生は、昔ながらの渋い絣模様ではなく、能衣装に想を得た華やかで大柄な絣を織っています。一般的な絣とは異なるんですが、でも着装美を考えると、すごく面白いイマジネーションが浮かんできます。
僕たちはイマジネーションでしかあの着物を着装したところはわかりませんが、その方がいいんです。実際にあれが着られると、そこには着る人の人格がかかわってきますので、それがイマジネーションの邪魔になります。それに、絣というのは素材と技法だけから出てくる模様です。友禅のように生地の上から染める模様ではありません。ああいう制約の大きい複雑な作業で着装美にチャレンジするのは新しいことです。これは近代主義のさらに先に進んでいるような気がしています。近代が産んだものはだめなものばっかりじゃないと僕は信じて、次の世代になにかを託していきたいと思うんです。
着物には着る人の人格がかかわってくる
長者町 いまのお話、新鮮でした。話の筋が多少それますけど、個人作家のつくる着物には作者の制作意図があり、それが「着物を纏う人の人格」と衝突することがあるということなのですね。作者からすると、着装してもらうことには悩みがともなうということなのでしょうか。ことはそう単純ではないのですね。
森口 僕の着物を着てくださる方は、当たり前ですがお人形さんではありません。ファッションショーならば、モデルは作者の意図に従って演じてくれるでしょうが、現実の女性がそんな配慮をして着物を着てくれるはずがありません。彼女たちは自分の人生を背負っていますから。
長者町 いわれてみれば、そうですね。誰だって、男にしたって、服選びは自分の人格の表現ですからね。そういう気持ちをもってないと、高級な着物を装っても、社会的なステータスを示す「制服」になってしまうわけだ。
森口 以前の僕は、そのことに気づかず、自分の制作意図が、僕の着物を着た女性の人格によって台無しにされていると思ったことさえありました。
長者町 深い話ですね。作者の主観を表現するという近代芸術の根本思想が、実際に身につける工芸品の分野に浸透してくると、そういう問題が生じるんですね。それで、どう解決したんですか?
森口 解決なんてできません。最初の「企画の目的」で、あなたは日本美術の近代主義は西洋美術の「様式」を模倣することから抜けだせていないといってましたが、僕の場合は、自分でいうのもおこがましいですが、様式の模倣を超えて、フランス留学で個人主義を身につけてきてしまったのかもしれないんです。
ですから友禅をブレイクスルーする前に、フランスで僕自身が解体されてしまったようなものです。帰国してから僕は、友禅の予定調和的な美の世界に浸っていいものかどうか悩みました。それはパリから戻った安井曾太郎が、帰国してから何年間も絵が描けなくなってしまったようなものかもしれません。
長者町 私は「台湾航路――同化政策にあらがった陳澄波と藤島武二」を書いてみて、極東の人間が西洋芸術を学ぶことの困難さを痛感しました。陳澄波の場合は東京美術学校から台湾に帰り、母国の暮らしを再発見することによって、藤島の場合は日本画壇の西洋化された風景画から逸脱することによって、自分たちが西洋人の描いた絵画から受けた最初の感動を取り戻すことができました。ですが、森口さんの場合は、京都という友禅染の本拠地のなかで、留学で身につけた個人主義を保持しなければならなかったわけだ。
森口 僕は目前の仕事をこなすことで、ここまでやってきました。傍から見れば、その過程が僕なりの、「近代主義」解釈だったのかもしれませんね……。そこには僕なりに行き着いた友禅のインテリジェンスが発揮されていたようにも思います。
長者町さんのいう「装飾」には、工芸家たちのそういうインテリジェンスが含まれているのだったら、僕はあなたの考えに賛成です。志村ふくみさんも、自然を使わしてもらいながら、自分たちの世界を慰めたり励ましたりしてくれるのが工芸の文化だといってます。
もしもそうしたインテリジェンスが現代人の心を救えないとすれば、そのときは工芸家の近代は、長者町さんがいうように終焉を迎えるべきだと思います。
長者町 私はこれから日本の芸術家のなかでも、とくに工芸家の近代主義についてもっと掘り下げなければいけませんね。
森口 長者町さんは、そういう問題にどんな答えをだされるんでしょうか……。
江戸時代の装飾
長者町 ところで江戸時代の工芸、私のいう「装飾」には、そんなインテリジェンスが自然とそなわっていたようにも思います。もちろん当時の工芸家、というよりも工芸職人は、仕事の注文主の要望に忠実でした。依頼主の方が職人よりも、作品の制作意図にかんしては相対的につよい決定権をもっていましたから。ですが、それでいて職人たちの力を借りなければ、江戸の民衆は自分たちの生き方を可視化することができませんでした。
さっき絣に言及されましたが、この絵を見てください。これは江戸後期の二代歌川春貞が描いた「夏美人図」という肉筆浮世絵です。この若い女性が着ている絣の着物や髪飾りにこそ、森口さんのいう工芸のインテリジェンスや、私のいう装飾が物語られていませんか?
江戸時代には工芸という、身辺の品々を集合する名詞がなかったので、当時の人は若い女性が身に着けている物を、着物、櫛、かんざしと個別に呼ぶしかなかったはずです。もっともこの女性が装着する品々にかぎっていえば、「小間物」という言葉があったのかもしれませんが……。
ですがこの女性と会う人は、それらの品々を通してこの女性の人となりを感じ取っていたことでしょう。ただ、それを表現する品々を包括する言葉(概念)がなかったのです。
それで後世の我々は、「工芸のインテリジェンス」や「装飾」という言葉を発案、あるいは再使用しなければならなくなっているわけです。これらの語句が適切か否かはともかく、工芸が近代化されていく過程で、この女性の楚々としたたたずまいを言い表す語彙が、我々の生活感覚から抜け落ちてしまったのでしょう。
描かれている女性は商家に嫁いだご新造さん、年のころなら三十才前の若奥さんのように見えます。もう結婚しているので、派手な装いは控えてすべてが地味です。でもそれがかえって、この人のもつほんのりとした色気と、落ち着いた生きざまを感じさせます。前近代の装飾品(工芸品)には、この女性のそんな人柄を世間に発信する機能があったわけです。
この絵をご覧になって、森口さんいかがですか?
森口 まず、この人はまだ二十歳になってないと思います。こういう雰囲気は十代でしょう。当時は結婚する平均年齢も低かったでしょうし。
明治になって黒田清輝が描いた「湖畔」の若い女性にも、この雰囲気は受け継がれていますね。あの女性が着ているのは絣じゃなくて、縦縞の着物でしたが……。
長者町 黒田の時代までは、西洋に学ぼうとする画家の近代主義と、江戸の装飾あるいは工芸のインテリジェンスとが共存していたんでしょうね。ところで工芸のインテリジェンスは、日本語でなんといえばいいでしょうか?
森口 さあ、難しいですね。「工芸の叡智」でしょうか。
長者町 そういう風に訳すと、だいぶわかりやすくなりますね。さらにもう一歩踏み込んで、これは意訳ですけど、「工芸に託されてきた生き方」というのはどうでしょうか。
森口 江戸時代の社会に生きていた人たちが獲得した叡智が、工芸には凝縮されているという意味ですか。
長者町 そうです。ただし、類型的な生き方に人々が自分を当て嵌めていくというのではなく、足立先生の例でもありましたが、まずはひとり一人の個人が自分の生き方を、着物や髪飾りのような品々に託して表現することからはじまり、それらが集積されて、工芸には社会や時代の生き方が託されているという社会通念が出来上がっていったのだと思います。
これが私の考えている「装飾」というものです。ですから、装飾とは「工芸に託されてきた生き方」のことであるといってもいいのではないでしょうか。
森口 なるほど。
長者町 肝心なことは、装飾とは人が自分の生き方を演出するために選択する、あらかじめ用意されている「ひな形」(テンプレート)ではないということです。「夏美人図」のご新造さんのように、自分で自分の人生をつくり、それを物によって表現する行為が装飾だということです。
森口さんは、そんな女性たちの自立した生き方に、着物づくりによって寄与してきたように、私には思えます。
外務省が構想した「日本の美」
森口 結局、近代の学校制度や、官設美術展の制度、そしてそういう場での西洋画、日本画、工芸というジャンル分けが、前近代の装飾を解体していったんでしょうね。
昭和三五年ぐらいですかね、外務省がつくった「日本の美」という映画があるんです。私の父の友禅を、女優の香川京子が着て、野村別邸の茶席で、松田権六の棗、荒川豊蔵の茶碗を使ってお茶を立てているシーンからはじまる、日本を宣伝するための映画だと思うんですが。そこには前田青邨の日本画や、棟方志功の創作版画も出てきました。しかし油絵や現代工芸は入ってなかった。ということは、外務省は日本の伝統的な生活文化を世界に見せようとしていたんでしょうね。
長者町 その映画がつくられた昭和三五年頃って、敗戦から一五年後ですよね。映画を製作した外務省や、知恵を授けた文化財保護委員会(現、文化庁)は、昭和三二年に、工芸は伝統技術を守るだけじゃなくて、そこに芸術性を加えなければならないと提唱しています。
森口 岡田譲あたりが中心でしたね。
長者町 大きく捉えると、日本は確かに戦争では負けたけども、文化では負けてないぞという気持ち。自負心をもう一度取り戻したいという意識が、当時の官僚たちのなかにあったんでしょうね。
森口 そりゃそうだと思うし、国民にもあったと思いますよ。僕も子供時分に、湯川秀樹博士のノーベル賞受賞や、水泳競技で欧米人を破った古橋廣之進のことが誇らしかった。戦争に負け、そこから立ち直るには誇れるものが欲しかったのです。
昭和初期の、あのエキセントリックな右寄りの人たちが陥った大和魂ではなくて、最初にいった「和様」に戻って考えるべきだと僕は思います。言葉で表現される先生方が、もう少し僕たちの誤解を招かない言葉を使ってもらえるとありがたいです。
パトリー
長者町 芸術家が近代主義を貫徹できなかった理由として、私は最初に掲げた「企画の目的」のところで、国民の「国家主義的心情」(ナショナリズム)による障碍を挙げました。では、仮に工芸が江戸時代の「装飾」のままであったとすれば、近代になっても工芸は国民の「国家主義的心情」と衝突しないですんだでしょうか?
私は、衝突しなかっただろうと思います。明治の日本人が、はたして江戸趣味の工芸を家に置いて満足したかどうかはわかりませんが、工芸が欧米人のオリエンタリズムをくすぐる江戸の装飾のままであったとすれば、欧米に日本を承認させようと望む国家主義者にとっても、工芸の存在は邪魔にはならなかったでしょうから。
実際、戦後になってそれを想像させる状況が、日本の工芸界に生じています。それは、文部官僚たちが伝統工芸展の創設を提起して、「伝統技術には日本人の魂が宿っている」という愛国的心情に訴えたときです。国家主義的心情と愛国的心情ではニュアンスが違いますが、日本人に自国には文化の根っこがあり、前近代から装飾(工芸)はそれを大切にしてきたと気づかせた点では、同じ機能をもってました。民衆の気持ちを拠りどころにしていた江戸の装飾が、戦後によみがえった瞬間でした。
森口 愛国的という言葉の英訳はパトリオティックで、愛国者(パトリオット)と同じ語源(パトリー)から派生した言葉です。パトリーというのは、山があって川が流れて田んぼがあって、農村があってという、あの静かな山里の風景そのもので、そここそ文化が育まれる場所だと思います。先ほどあなたは、パトリーとナショナリズムが類似しているかのように話されましたが、僕の考えでは両者は別物です。パトリーとは、「国」ではなく、「郷」なんですから。
そういう意味では、僕は日本工芸会が琉球の紅型までを対象にして公募展を開くようになったことを、悩ましく思っています。地域の産物や文化を考えることがパトリーだったのに、日本伝統工芸展は全国一律で各地の工芸を審査しだしたんですから。
長者町 全国一律で審査するか、郷土ごとで審査するかといえば、私も郷土ごとの方がいいと思います。地域から文化を考えるという意味では。ただ、どちらにしても、審査するときの基準はなんなんでしょうか。全国一律のときは「国家のナショナリズム」で、郷土のときは「地域ナショナリズム」だとすれば、どのみち両者の審査基準は「集団」のイデオロギーだといわざるをえないでしょう。
つまり、私たちの人生や芸術は、どう転んでも集団のイデオロギーから逃れられないわけで、そういう意味で、私は戦前のナショナリズムは戦後のパトリーと地続きだと考えているんです。パトリーとはいかなる集団の、いかなるイデオロギーだったのか? 私はそこに関心をもっています。
森口 僕はイデオロギーには食傷しています。そういうものに絡めとられる前の工芸を大切にしたいんです。
工芸にも「近代主義」があった
長者町 私も森口さんと同じように、工芸をその原点に戻したいと思っています。そのために、前近代の装飾とはいかなるものだったかと問うているのです。江戸の装飾と、最近の伝統工芸との類似に注目しているのも、同じ気持ちからです。
それにしても、明治初めの一八七〇年頃から二〇〇〇年ころまでの約一三〇年間、工芸の根底は伝統工芸であるにしても、他方では近代主義の工芸も盛んでした。それは、帝展に工芸の出品が認められた昭和二年(一九二七年)以降のことです。戦前の昭和期、そして戦後しばらくまでの革新的工芸には、西洋芸術の様式が反映されています。
たとえば私は駆け出しの学芸員だった頃、「モダニズムの工芸家たち」という展覧会を企画しています。高村豊周の「挿花のための構成」(一九二六年)はそのときの展示品です。アール・デコの造形的源泉だったキュビスム彫刻やバウハウス・デザインの幾何形態が、花瓶に組み込まれています。高村は洋行していないので、彼はそれらの形態を、西洋で出版された雑誌などから取り入れたはずです。
絵画の分野でも、留学からの帰朝者は西洋絵画の技法を日本に輸入しましたが、そのひとりだった藤島武二は、バタ臭い日本女性像や日本風景を描くことに満足できませんでした。皇室の依頼で日の出の風景を描きはじめたときも、国内の写生では西洋絵画の精神が掴めないと感じた藤島は、関東軍と匪賊が戦闘中の蒙古の砂漠にまで出掛けて「蒙古の日の出」(一九三七年)を描きました。
辻晋堂は、唐代の奇人である寒山拾得に想をえて、「拾得」をつくっています(一九五八年)。誰も見たことのない人物とはいえ、実在したかもしれない人間を、非具象の形態で作品化しているわけです。こういう新しい様式への挑戦には、戦後のパリに登場したアンフォルメルの影響があったと想像されます。
森口 辻晋堂は一九六〇年のニューヨーク・アートフェアで大喝采を受けています。
長者町 辻晋堂の作品は、いまの我々の目から見ると、日本的あるいは宗教がかって見えますが、外務省が製作したさっきの映画に出てこないところを見ると、昭和三五年(一九六〇年)頃の官僚の目には、彼の作品は「日本の美」とは映っていなかったのでしょう。
森口 辻晋堂がとつぜん話題にでてきて驚いています。僕にとっては美大の先生というよりは、友人のお父さんとして接する機会が晩年までつづきましたので、人となりを知りえた者として、すこしちがった感想があります。あの方は禅宗の坊さんで、ほんとうに深い修行をつんだ方です。ですから、彼の精神的な構造からいったら、作品がアンフォルメルに影響されているというのは違うと思います。
理論の東京と、自由な京都
長者町 今日のテーマになるかどうか分からなかったので、言い淀んでいたんですが、東京と京都では西洋芸術の輸入の仕方が違うように思います。たとえば、辻晋堂が「拾得」をつくった一九五八年の十年前に、京都では八木一夫を中心にして走泥社というグループが結成されていますね。その活動は前衛陶芸の分野で一世を風靡して、八木たちの作品は京近美にはたくさん収蔵されているんですが、私が在籍していた一九九〇年代までの東近美工芸館には、たしか二点しか収蔵されていませんでした。それも寄贈されたものでした。その後はすこし増えているようですが、それでも合計で五点です。これは、なぜかっていうところなんです。
森口 そうだよね。
長者町 これ結局、文化庁の技官や工芸館の学芸員たちのあいだでは、八木の作品をどう評価していいのか理論的に説明がつかなかったからだと思います。それで収蔵委員会のテーブルに出てこなかったんでしょう。東京というところは、さっきの外務省映画でもそうでしたけど、欧米を意識したイデオロギーのつよい土地柄なんです。理論で説明がつかないものに二の足を踏むという東京の体質。あるいはアカデミズムの体制。これが東京の工芸家が信奉していた近代主義の影の部分だったと、私は思っています。
森口さんから見ると、馬鹿々々しいと思われるでしょうね。京都の方は自由ですから。
森口 東京と京都の政治的役割の違いはどっちでもいい問題で、いまこれから何をしようとしているのかを議論し、どの地点からスタートするのかを考えるのが今日のお話ではないですか?
長者町 そうでした。ただ森口さん、そうやって整理して一件落着にすると、東京の近代主義が多くの美術愛好者を魅了してきた理由と、いまその破綻を前にして、近代主義のつぎに来る芸術を考える方策が見えなくなってしまいませんか? そもそも芸術家が西洋芸術から学んだ、時流を刺激してでもなにかを表現しようとする「意志」は、もう必要とされない時代になっているのでしょうか?
たとえば、高森昭夫の「General and Emperor(元帥と天皇)」(二〇〇一年)という陶彫を見てください。 敗戦国の昭和天皇がマッカーサーとはじめて面会したときの写真は、誰もがどこかで見たことがあるでしょうが、高森はそのときの天皇の落剝したようすを、さらに誇張してカリカチュアに仕立てています。高森はシアトル大学の先生だったんで、工芸に政治性をもち込むことに躊躇はなかったんでしょうが、我々がそのことを指摘してみても、それは近代主義に通有の政治性を批判しているだけで、近代主義の根幹にある表現する「意志」からなにかを学ぶことにはならないでしょう。
もうひとつ、こんな作品もありました。これは日本工芸会の創立に寄与した松田権六の「動物文膳 熊」(一九二七年)です。戦前の作品です。駒込の東洋文庫にいた松田は、朝鮮の楽浪遺跡で発掘された紀元前一世紀から紀元後一世紀ころの「銅筒」を見る機会があり、そこに象眼されていたクマの文様を写してこの作品をつくりました。東洋の古代文様を輸入して、(当時の)現代芸術に蘇生させたわけです。これは、彼の帝国美術院展覧会の最初の入選作となりました。
森口 特別な選ばれた人やね。
長者町 先見の明がある人ですよね。伝統技術にも芸術性を見出ださなければならないことを、松田は戦後の文部官僚に先んじて見抜いていたんでしょう。
森口 そういう力のある人ですよ。あの方のご意向で、日本伝統工芸展はできたようなものです。
長者町 ただ森口さん、帝展というのはどういう場だったかっていうと、これは近代芸術の舞台でしたね。
森口 そうですね。
長者町 帝展は欧米に、日本にはこんな芸術があるんだぞということを発信するための舞台だったじゃないですか。
森口 長者町さんがおっしゃってるのはそういうことなんですね。
長者町 ですから戦前の松田権六は、近代主義の文脈のなかで制作していた、と私は思います。でも松田権六は、そのなかで終わらなかった。しかも松田だけではなく、若いときにアール・デコに倣っていた工芸家でも、高村豊周のように戦後になって伝統回帰した工芸家は少なからずいました。こうした現象には、パトリーへの目覚めだけでは説明できないもの、たとえば「東洋の古典につながる日本芸術」への郷愁とでもいったものがあったといえないでしょうか。
森口 戦後になって、かつての官展の悪弊を改めたいとして、日本工芸会の設立に奔走された松田権六先生でした。松田さんは帝展の轍は踏まないとおっしゃっていました。僕は父の森口華弘から、昭和初期の帝展や新文展の動きを聞かされています。父はもう二度と国がやってる展覧会には出さない、自分は美しいものをつくりだすんだといってました。
公募展には出すまいと心に決めていた父でしたが、日本工芸会の趣旨にはおおいに賛同していました。この国の近代化のお役に立てると思って、日本伝統工芸展に参加したんでしょうね。その後次第に認められていった経緯をすぐそばで見ていた僕としても、「自由」を見いだし、自らの宇宙を探索する場として日本伝統工芸展にかけるところ大です。
石黒宗麿の生き方
長者町 ところで、美術評論のような話に終始するとあと味が悪いんで、つぎに繋がる話をしませんか。
私はこのところ石黒宗麿のことを取材しているんですが、あの人は作品制作と同時に、自分の人生を創作することに執念を燃やした人ですね。彼は陶芸家でしたが、でも江戸時代の民衆が工芸品に自分の生き方を託していたことに気づいて、そんな生き方を自分でもやってしまったんだと思います。
森口 はい。
長者町 たとえば、「柿釉壺」(一九三八~四二年)。ありふれた壺に見えるかもしれませんが、制作年代を見てください。戦争一直線だったこの時期は、新文展(帝展の後身)の作家が美術界のトップに君臨して、技巧と色彩を駆使した華やかな文様の工芸品が展覧会場を支配していました。そんなときに石黒は、装飾とは作品に付加価値をつけ加える脇役ではない。壺の形と色それ自体が作品の主役なんだと主張していたんです。
もうひとつの、「ケダモノ文鉢」。宗麿は狩が好きで猟犬を飼ってたんですが、それはともかく、この作品では器物の形は意味をもってません。それは白いキャンバスにすぎない。彼の後半生の陶器には、文様だけで装飾にしてしまった作品が多くなりました。
石黒は評論家が話すような工芸品鑑定の規範に従うことに抵抗していたんでしょうね。いわば工芸の既成権力にひれ伏さなかったんです。その生き方が、彼の陶器を愛好する人たちに、国家や会社の抑圧から自分を解放していく勇気を与えました。私はこういう機能が、これからの工芸が担う役割だと考えています。
森口 僕は安心しました。日本工芸会では松田権六先生と反りがあわず、難しいことがたくさんあったと聞いていますが、一九六七年の一年間、僕は石黒先生の運転手というか、電話がかかってきてタクシーが来ないから迎えに来いっていわれて、しょっちゅう八瀬のお宅にまでお迎えに行ってました。六八年六月に亡くなるまで、息子のように便利に使ってくれたんですけど、ほんとうにかっこいい人でした。
お宅で僕がお茶をいただいていると、石黒さんは急に立ち上がって、鉄砲で庭に出てきたタヌキをバーンと撃ってました。それほど神経を張りめぐらせていたんですね。八木一夫も石黒さんにはかなわんとおっしゃってました。近代主義以後の工芸を、この人からスタートさせるんだったらいいんだけど、易しくはないでしょうね。
長者町 さっきの「夏美人図」で、ご新造さんが着ていた絣から約一五〇年間をワープして石黒宗麿の装飾にたどりついて、装飾をそこから再スタートさせればいいと考えています。
森口 大賛成です。
長者町 嬉しいです。
森口 石黒さんには文人の構えと、希代の職人魂がありました。なんていうかな、サムライでした。
長者町 そういう意味でね、この人は自分なりの人生をつくった人でした。とにかく常識が嫌いで、独自な目で作品や人生をつくった人のようですね。
森口 でも石黒さんにとって、中国文化はひとつのお手本でしたね。あの人の漢詩はよかった。その辺はどう思いますか?
長者町 私はいつもそこでつまずきます。日本は弥生以来、中国や朝鮮半島からやってきた文化を取り入れて、日本なりのものにしてきました。つぎの時代が来ると、また新しい文化を消化して、輸入文化の地層をつくってきました。
ですが、中国ではちがってた。漢民族だって、唐や明の後には異民族の元や清の文化を輸入していた。だから中国にも輸入文化の地層があるじゃないかといわれればその通りです。でも、宋の青磁、元の染付、明の赤絵、清の粉彩のあいだには、因果関係が見つけられません。バラバラなんです。私はそれを、台北の故宮博物院で陶磁器の年代別展示を観たとき悟りました。
だから石黒宗麿が中国陶磁を写すことから工芸家としてのキャリアをはじめたのは事実であるにしても、また、水墨画に継承されてきた中国の文人精神にシンパシーをいだいていたのも事実ですが、石黒が共鳴した中国陶磁や文人精神は、すでに質的変化を遂げていたのではないですか。石黒にとって、それらは「直感」の源泉でしかなかった……。
森口 漢字。 漢字文化はどうですか? さっきの辻晋堂も漢詩にすぐれた人でした。読み下すことなく、漢詩を読んでいました。石黒宗麿も漢詩をたくさん読んでいます。僕は、先生の「大巧如拙」という書を、いまも座右の銘として大事にしています。
長者町 「大和心(やまとごころ)」にたいする「漢心(からごころ)」の系譜に、辻晋堂や石黒宗麿はつらなっているということですね。永平寺で得度した辻は当然として、異端の人生を歩んだ石黒も、近代主義に代わるものとして文人精神にシンパシーをいだいていたことでしょう。
連帯
森口 石黒宗麿の世間とのかかわり方を見ていると、「連帯」という言葉が浮かびます。フランス語でいうソリダリテですが、これは人と人を結びつけるものではあっても、近代日本の中央集権や国家主義のように政治性を帯びた結びつきではありません。
長者町 フランス人の連帯は、公(おおやけ)を頼りにしていませんね。私のささやかな体験でも、その筋のお達しでアパルトマンの大家が各室の玄関扉を、鉄の防火扉に取り換えようとしたところ、居住者たちが役所と掛け合って不燃木材の扉に変更させたことがありました。これなんかフランス人の連帯気質をよく表した出来事だと思います。
森口 その辺がフランスの面白いところですね。彼らは公権力に依存しないところがある。ノートルダム寺院の尖塔が焼け落ちたときも、コンパニオンという、宮大工や石工の職能組合が自発的に復興仕事を買って出たようですね。これは面白い組合組織で、親方は仕事を教えて欲しいという人が来たら、それがどんな人でもかまわず、ねぐらと食べ物を与えて、三年間は面倒を見る義務があるんですって。親方はその人を他地方の親方のもとでも修業させて、十年で一人前の職人にする。千年はつづいている慣習らしいです。僕たちの日本工芸会も、政府組織とは一線を画した公益社団法人であることが誇りです。
長者町 一般論ですが、芸術家が主催する展覧会は、国家が保護するようになるとつまらなくなりますね。
森口 三越で開催する日本伝統工芸展は、日本工芸会と文化庁との共催ですが、僕は文化庁が何とかしてくれるという風な考え方をもてない人間です。でも、文化庁には理解してほしいと思います。地方の支部活動が難しくなってきています。
ところで、長者町さんと一緒だった日本工芸会の西部支部展での審査は愉快でしたね。言葉を使って長者町さんが見どころを変えてくれた作品が最高賞になったんですから。
長者町 あれは二〇二三年でしたから、パリで会ってから三八年ぶりの再会でしたけど、ブランクをまったく感じなかった。
森口 作品をつくらない人が、しっかりものを言うて欲しいと思います。
長者町 だけど私はもう評論家じゃないんですよ。小説家としては無名ですけど、互いに人間論を話したくて、今日はこういう場をもうけました。
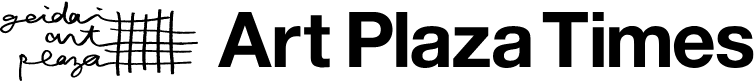

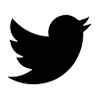 ツイートする
ツイートする
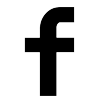 シェアする
シェアする